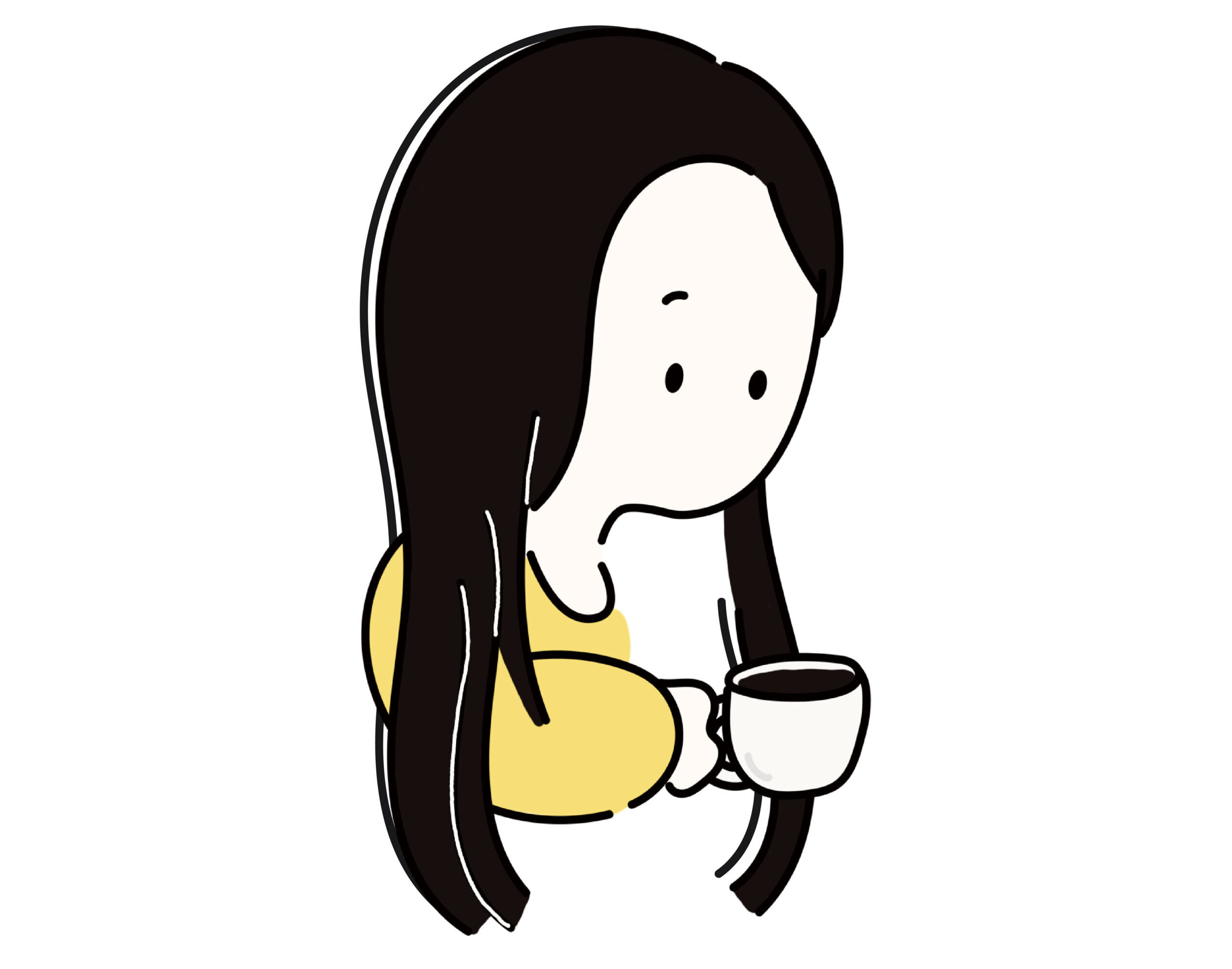まず、社員のみなさんにこんな問いかけをしてみてください。
「当社の経営理念、すぐに答えられますか?」
……もし、明確な答えが返ってこなかったとしたら、少し驚くかもしれません。
でも、それで終わりにせず、もう一歩だけ踏み込んでみてください。
「では、その経営理念に基づいて、あなたは何をすべきだと思いますか?」
この質問にもスッと答えられる職場であれば、経営理念がしっかり現場に根づいている証拠。
そうした組織は、きっと“強さ”を持っているはずです。
しかし実際には、こんな声が返ってくることもあります。
「経営理念……たしか、ポスターに書いてあったような…」
「何をすればって……うーん、とにかく頑張る?ですかね…?」
こうした反応は、決して社員のやる気がないわけではありません。
むしろ、評価項目や行動の基準があいまいなままでは、「どう動けばいいのか」が分かりづらくなってしまっているのです。
つまり、会社が大切にしている価値観や方針が、現場まできちんと届いていない状態ということ。
これが、”理念があるのに活かされていない”という、もったいない状況です。
経営理念を「評価項目」に変えるには?
経営理念は、会社にとっての「羅針盤」。
でもそのままだと、少し抽象的で、日々の仕事にどう活かせばいいかが分かりづらいこともあります。
だからこそ、評価制度では「理念を行動に変える工夫」が欠かせません。
たとえば、会社が
「お客様との信頼関係を大切にする」
という理念を掲げているとします。
これを評価項目として活かすなら、次のような行動が考えられます。
- 聞かれたことだけに答えるのではなく、一歩先を考えて提案する
- 対応が遅れそうなときは、事前に理由と目安を伝える
こうして具体的な行動に落とし込むことで、社員にとっても
「自分は何を期待されているのか?」
が明確になります。
日々の業務でも迷わず行動できるようになり、軸のブレないチームづくりにもつながっていきます。
経営理念を“現場で使える言葉”に変えること。
それが、評価制度を機能させる第一歩です。
評価制度の本当の役割とは?
「評価制度」と聞くと、まず思い浮かぶのは
“査定”や“人事考課”といったイメージかもしれません。
もちろんそれも重要な役割ですが、実はそれだけではありません。
社員に対して、会社が「何を期待しているのか」を明確に伝えること。
それも、評価制度が果たす大切な役割のひとつです。
評価項目を通じて、経営理念を具体的な行動に落とし込むことができれば、
社員は「どう動けばよいか」を理解しやすくなります。
その結果、日々の業務でも迷わず行動できるようになり、
組織全体の方向性にも一貫性が生まれます。
では、今の評価制度はしっかり機能しているでしょうか?
- 経営理念を、具体的な行動として表せているか?
- それが、現場で実際に活かされているか?
こうした視点から、評価制度を見直してみることで、
経営理念が現場で“動き出す”きっかけになるかもしれません。