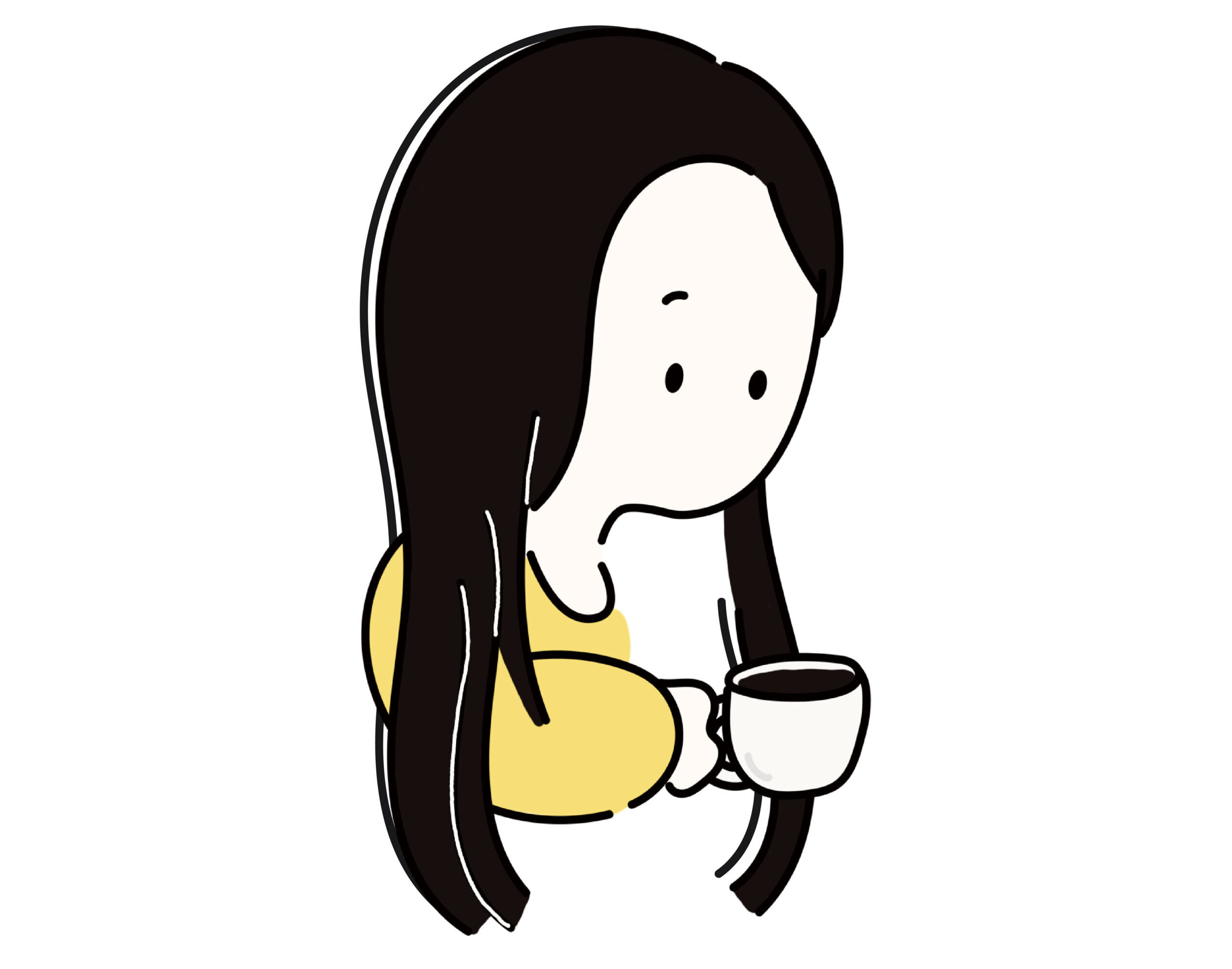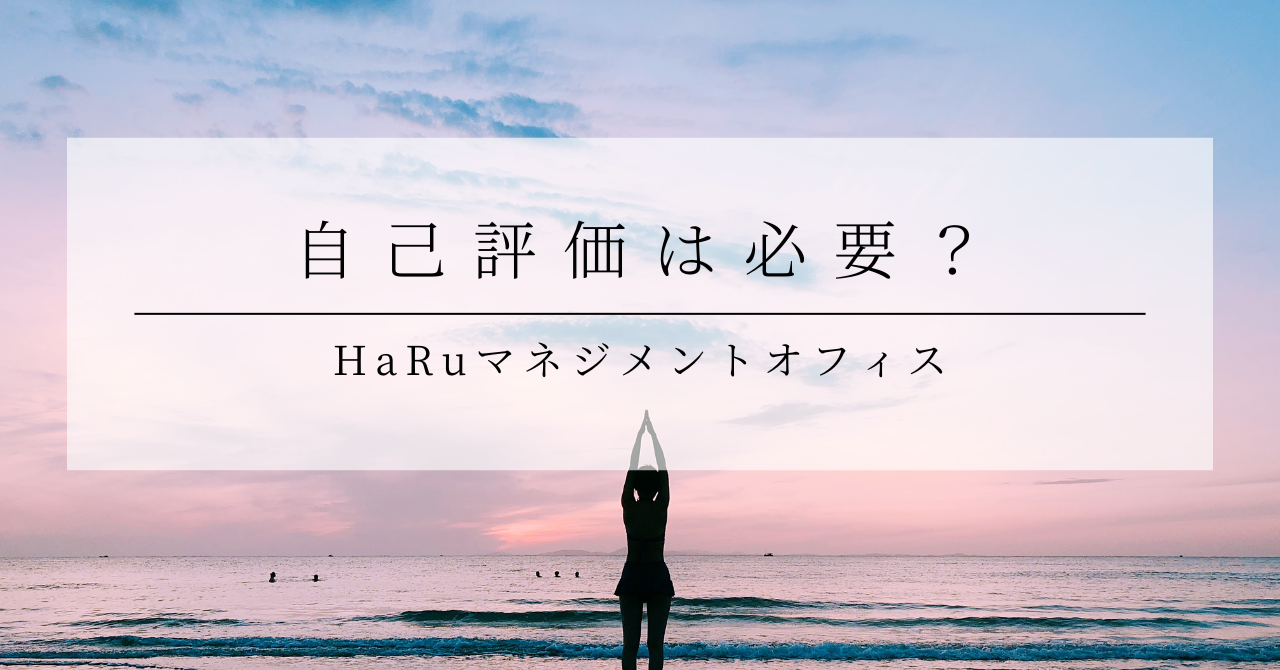「自己評価って、本当に必要なんでしょうか?」
そう感じている方も、実は少なくありません。たしかに、最終的な評価は上司が行うことが多く、「自己評価は形式的なもの」と思われることもあります。
ですが、先日、管理職になったばかりの方と話す中で、印象に残る言葉がありました。
「自己評価と上司の評価が、あまりにもズレている社員って要注意なんだよね」
なるほど、と思わされる一言でした。
たとえば、上司が「もう少し改善が必要」と感じているのに、本人が「自分はよくやっている」と高く評価しているとすれば、それは認識のズレです。
このズレには、業務理解や評価基準の共有不足、日頃のコミュニケーションなど、さまざまな原因があるかもしれません。
逆に、自分を必要以上に低く評価してしまうケースもあります。
その背景には、自信のなさやモチベーションの低下が隠れていることも。
こうした状況を見逃さないためにも、自己評価は有効な手がかりになります。
そして何より、このような自己評価と上司評価のズレに早めに気づくことは、社員の退職を未然に防ぐきっかけにもなります。
「頑張っているのに認められていない」
「上司は自分を正しく見ていない」
そういった小さなすれ違いが、不満や誤解へと発展してしまうことも少なくありません。
定期的に自己評価を取り入れ、その結果を丁寧にフィードバックすることで、信頼関係の構築やエンゲージメントの向上にもつながっていくはずです。
自己評価は、単に評価のための材料というだけではなく、上司と部下の間にあるギャップに気づくための“対話のきっかけ”でもあります。
また、社員自身が自分の強みや課題、今後の目標について考える機会にもなります。
評価制度は、一定の基準で線を引くための仕組みです。
ですが、そこに自己評価という視点を加えることで、納得感のある制度運用へとつながっていく可能性があります。
「うちの会社に、自己評価って本当に必要なんだろう?」
そんなふうに感じたときは、一度立ち止まって、評価制度の目的や使い方を見直してみるのも良いかもしれません。
制度の活かし方次第で、社員の定着=経営の安定へとつながる第一歩になることもあります。